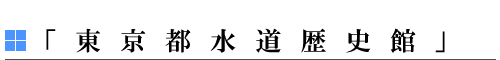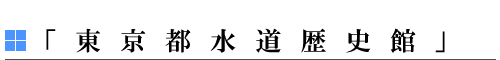|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Home |
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
東京都水道歴史館は、江戸時代から近代上水道事業が始まった明治時代、現在までの東京都水道 |
|
| |
事業の歴史を紹介した資料館です。見学は無料で、順路は2階からです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
2階展示室では、江戸上水の歴史などが紹介されています。東京の水道の起源は、1590年 |
|
| |
徳川家康が江戸入府にあたり家臣につくらせた小石川上水(後の神田上水)とされています。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
下町の住居(長屋)の再現などが実物大で展示されています。井戸そっくりの水道汲み上げ施設、 |
|
| |
路地の真ん中に設けられていた下水、各戸内の生活の様子などが具体的に再現されています。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
上水井戸と木樋(もくひ)。上水井戸は昭和57(1982)年、千代田区で発掘されたもので原形をよく |
|
| |
とどめています。木樋には、角型、丸型、三角型があり、角型が最も広く用いられていたようです。 |
|
| |
どのように使われていたかはこちら。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
発掘された江戸上水。平成3(1991)年、千代田区丸の内の旧都庁舎跡地から発掘されたものです。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1階展示室では、近代水道の歴史などが紹介されています。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
共用栓や消火栓など。写真右は蛇体鉄柱式共用栓という明治時代末頃から大正時代末頃まで使わ |
|
| |
れていた共用栓で、水の出口が竜を型どっています。後の水道の「蛇口」の語源となったともいわれ |
|
| |
ています。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
馬水槽(ばすいそう)という公共水道施設のレプリカ。馬水槽はロンドン市牛馬給水槽協会から東京市 |
|
| |
に寄贈されたもので、
実物は新宿駅東口に設置されています。この共用栓には、牛馬用、犬猫用、人 |
|
| |
間用の3つの水飲み場が設けられていました。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
水道本管。この中で最大の管は口径2900mmあり、鋳鉄製の水道管の中では日本最大のもの |
|
| |
です。羽村取水堰から村山・山口貯水池までの導水管に使用されています。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
【 公式ホームページ 】 |
|
| |
東京都水道歴史館 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|